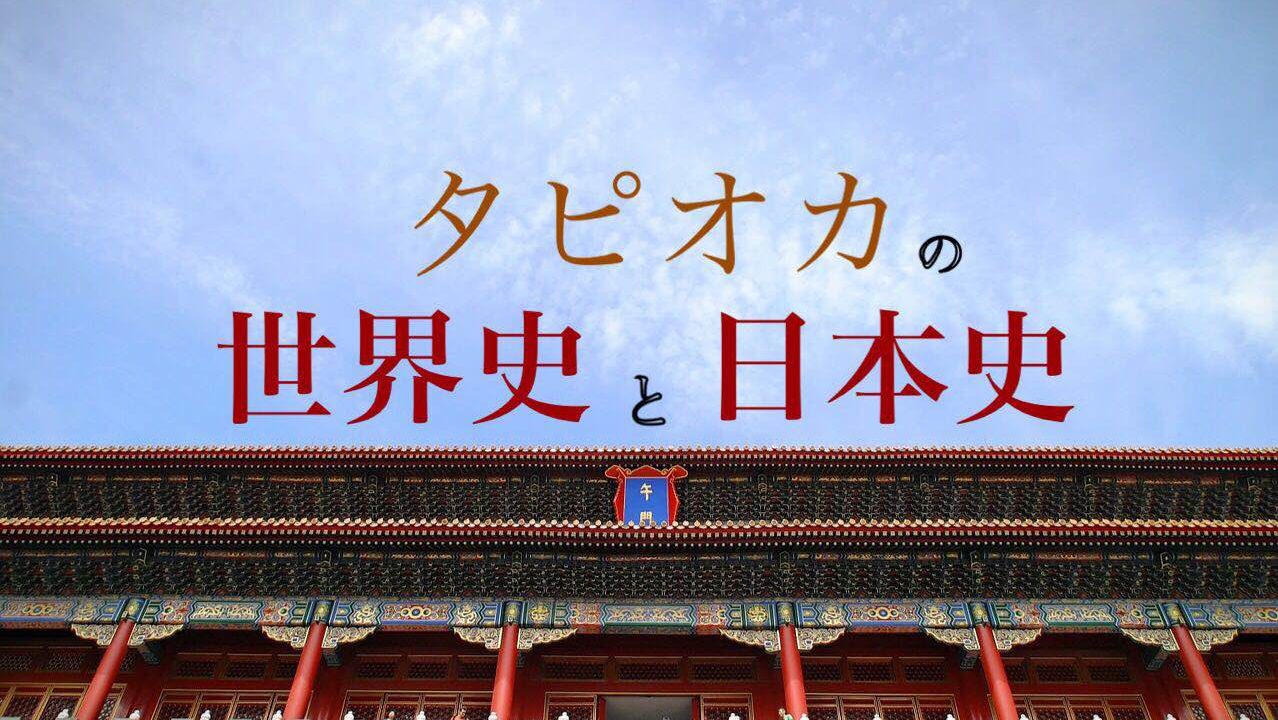そんな疑問にお答えします。
日本では、2017年~2019年にかけてタピオカが爆発的に売れ、タピオカ店舗が急増加したタピオカブームが起きました。
それに伴い、タピオカ認知度が飛躍的に上昇しましたが、そもそもタピオカの起源はどこから来たのでしょうか?
日本語での情報が少なかったので、英語や中国語の情報などを確認して、タピオカの歴史を時系列順にまとめました。

キャッサバ栽培からタピオカ誕生までの世界史
 タピオカの原料がキャッサバというイモ類の食物だということは、ご存知の方も多いとは思います。
タピオカの原料がキャッサバというイモ類の食物だということは、ご存知の方も多いとは思います。
キャッサバのデンプンを水に溶かして丸められたのが、タピオカ(パール)となります。
なるほどー。そもそもキャッサバっていつ頃から食べ始められたの?
約1万年前【南米】キャッサバの原型の栽培が始まる

現在栽培されているすべてのキャッサバの原型となったこflabellifolia亜種の分布は中央ブラジル西部を中心としており、ここで少なくとも1万年前には栽培が始まった。
1万年前!?

現存する最も古いキャッサバ栽培の証拠は、エルサルバドルにある1400年前のマヤ遺跡ホヤ・デ・セレンで見つかった。食料用の作物としての有用性から、スペインによるアメリカ大陸の植民地化が始まる15世紀末までには南アメリカ北部、中央アメリカ南部、西インド諸島の人々の主食となっており、(後略)。
南米より始まったキャッサバの栽培は、食料としての有用性からそのままアメリカ大陸を北上していったようです。
ちなみに西インド諸島は、インドではなくカリブ海のあたりの島々ね(今調べた)

キャッサバは今でもブラジルの伝統料理として食べられています。揚げて食べたり、粉にして料理にかけて食べたりと人気です。ちなみに在日ブラジル人の多く住んでる群馬県の邑楽町では、寒さにも強いキャッサバが栽培されており人気を集めてるらしいです。
キャッサバ料理ふつうに美味しそうで、お腹すいてきた。。。
16世紀【アフリカ】大航海時代に海を渡り主食として持ち込まれる

キャッサバは中南米原産のイモ類だが、アフリカでは既に16世紀に、またアジアでも19-20世紀に拡大した。
16世紀になると、遂にキャッサバはアメリカ大陸では留まらず、西洋人によって海を渡り広められていきます。

このうちアフリカにおけるキャッサバ栽培の第一の契機となったのが、コンゴ王とポルトガル人との緊密な関係と考えられている。第二の契機は、後の植民者による救荒対策としての栽培奨励であり、またより重要なのはキャッサバが現地の農法に適合していたことであるとされている。
スペインやポルトガルが世界を席巻していた大航海時代に、キャッサバはアフリカにも広まりました。食料として優れているうえに、現地の農法にあっていたという点もあり、アフリカ大陸ではキャッサバは主食として広まっていきます。
日本には鉄砲やらキリスト教が伝えられた時代だけど、アフリカではキャッサバなのね。。。φ(・_・”)メモメモ
19世紀【アジア】台湾政府から清朝へ「珍珠粉圓」が贈呈【タピオカの記録】
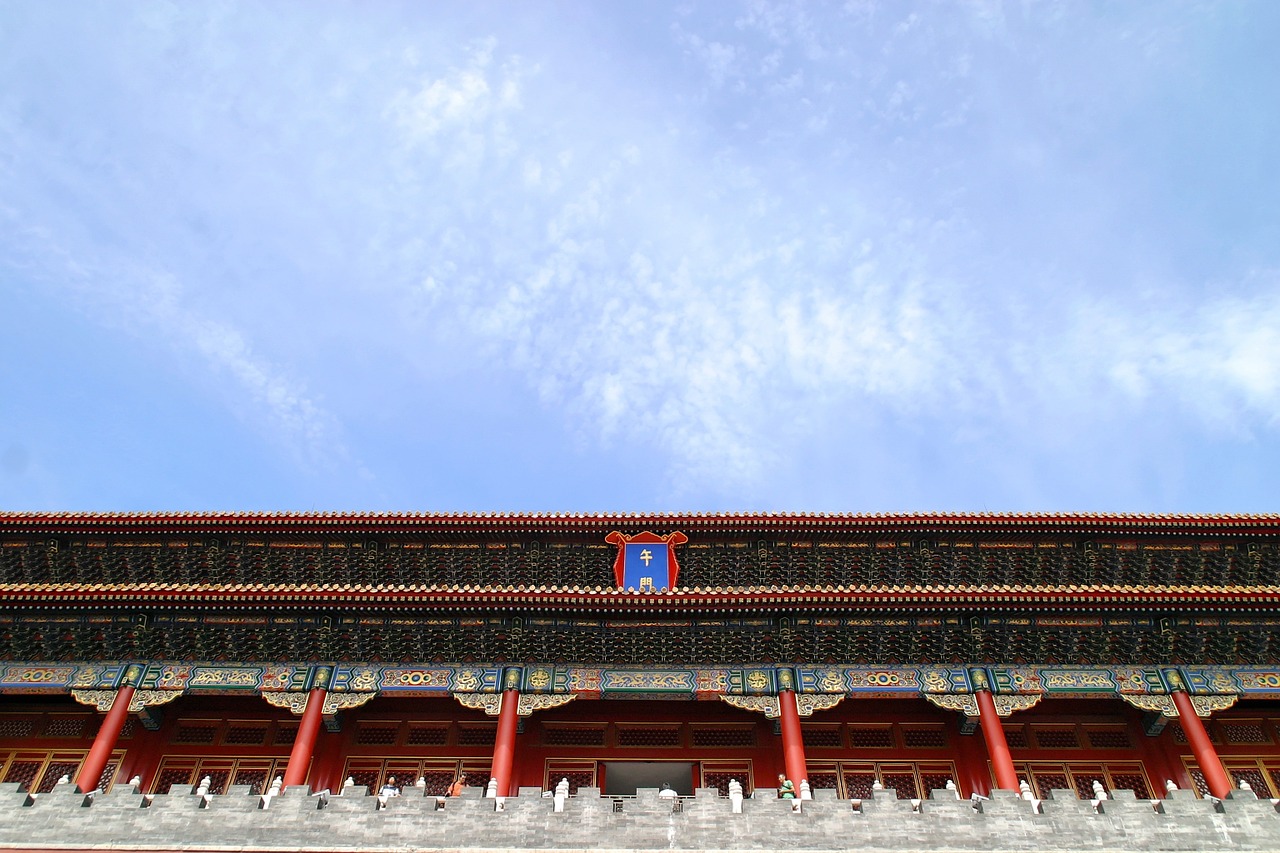 正確な時期は分かりませんが、19世紀に入るとアジアにもすっかりキャッサバは広がっていました。
正確な時期は分かりませんが、19世紀に入るとアジアにもすっかりキャッサバは広がっていました。
そして、いよいよキャッサバが馴染みある形に進化を遂げる時期でもあります。
關於具有台灣特色的“珍珠粉圓”,相傳是清朝慈禧年間進貢的獻壽禮,當時的台灣府用木薯粉為主要原料代替糯米做成類似元宵的“粉圓”甜羹,讓慈禧嘗後讚不絕口。從此在台灣即成為家喻戶曉的可口點心,至今歷久不衰。後來陸續經過食品專家將粉圓改良,使它光滑如同珍珠般閃亮動人,因此又稱“珍珠粉圓”
引用:中文百科 粉圓
なるほど、分からん。
19世紀の中国清の時代に、台湾政府から中国清へ「珍珠粉圓」が送られたとの記録があるの。
珍珠粉圓ってなに?

なるほど!
その頃には、「珍珠粉圓」は台湾のおやつ的な食べ物として親しまれていたようです。
やがてそこから表面を滑らかに真珠のように輝かせた、今でいうタピオカ(パール)が誕生します。
20世紀【アジア】戦時中の食料としてのタピオカ

耕作が簡単なタピオカだが、栄養価は乏しい。「ビタミンが足りず、病院は脚気(かっけ)患者であふれていた」とペナンの三菱商事の現地法人で勤めていた元医師ピーター・バニアシンガム(89)は振り返る。(中略)
戦後の食糧不足を補うため、日本は、アジアからタピオカの輸入を始める。地元ジャーナリストは言う。「大東亜共栄圏ではなく、共“貧”圏だった」
丸いタピオカが台湾でミルクティーに入れられ、世界各地で人気を集めるのは、一九九〇年代。アジアが成長軌道に乗ったころだ。
記事の中ではキャッサバとタピオカの区分けが曖昧ですが、戦時下で食料として食べられていたのは事実のようです。タピオカには栄養価の乏しい貧乏食といった時代もあるようです。
21世紀【世界】各国のキャッサバ生産状況と工業化原料への発展
 ちなみにキャッサバは世界各地に広まった後も、そこから独自の発展を遂げていきます。
ちなみにキャッサバは世界各地に広まった後も、そこから独自の発展を遂げていきます。
中南米:伝統的食料
アフリカ:主食(トウモロコシに次ぐ第二の主食)
東南アジア:食用・輸出用作物・工業化原料
特にタイやベトナムといった国々では、タピオカの原料として輸出業が盛んです。
ちなみに工業用原料とは製紙、プラスチック、化学製品に用いられるためのでん粉成分とのことです。
キャッサバの進化すさまじくね?
タピオカでん粉については、以前は原料のキャッサバが南部で生産されていたものの、東南アジアの安価なキャッサバおよびタピオカでん粉の輸入により、キャッサバ生産は大幅に縮小した。現在、タピオカでん粉の生産は、キャッサバの主産地であるタイやマレーシアの工場に委託されており、台湾での生産量は非常に限定的である。
台湾国内で作られるタピオカ工場のタピオカも、多くを東南アジアからの輸入に頼っているようです。
タピオカミルクティーの世界史
 19世紀には台湾でおやつ感覚で食べ始められていたタピオカパール。
19世紀には台湾でおやつ感覚で食べ始められていたタピオカパール。
それが、ついに1980年代にタピオカミルクティーに進化を遂げます。
タピオカミルクティーの起源には二つの説があるらしい。
1980年代:タピオカミルクティーの起源として春水堂と翰林茶館
 説1:台中の春水堂オーナーの劉漢介が由来な説
説1:台中の春水堂オーナーの劉漢介が由来な説
 説2:台南の翰林茶館オーナー涂宗和が由来な説
説2:台南の翰林茶館オーナー涂宗和が由来な説
ここでは文献の多かった春水堂の方のストーリーを載せていきます。
1980年頃 春水堂創設者が台湾茶を冷やして出すというアイデアを思いつく

The founder, Liu Han-Chieh, first came up with the idea of serving Chinese tea cold in the early 1980s after visiting Japan where he saw coffee served cold.
引用:CNN Travel Bubble tea: How did it start?
時は1980年代の初頭、春水堂創設者のLiu Han-Chiehが日本を訪れます。その際に提供されるアイスコーヒーを見て、中国茶を冷やすというアイデアを思いついたようです(当時の日本はドトールやプロントが出店数を伸ばしていたコーヒーブームでした)
え、タピオカどうこうよりも、それまで中国茶は冷やして飲まれてなかったの??
1983年 春水堂1号店が台湾台中にオープン
春水堂を設立。1号店として、台中府後街に四維本店を開く。
当時の店名は「陽羨茶行(ヨウケン茶屋)」。台湾で初めてカクテルシェーカーを使い、伝統のホットティーから画期的なアイススイートティーを開発し、一躍話題に。
画像&文章引用:春水堂公式HP 春水堂とは
そして、今の春水堂の原型といえるが「陽羨茶行」がオープンします。今では一般的な、熱いお茶を提供直前にシェイカーで冷やすスタイルもこの時からはじまったようです。
冷やすアイデアってこういうことね!直前に一気に冷やすことでお茶の香りも逃がさず閉じこめるらしいよ(何かに書いてあった)
1987年頃 タピオカミルクティーの誕生
ローカルフードのタピオカを濃厚なミルクティーにミックスした「タピオカミルクティー」を発明。国民的人気ドリンクへと大ヒット。のちに世界的にもタピオカドリンクのブームが広がる。
画像&文章引用:春水堂公式HP 春水堂とは
Then, in 1988, his product development manager, Ms. Lin Hsiu Hui, was sitting in a staff meeting and had brought with her a typical Taiwanese dessert called fen yuan, a sweetened tapioca pudding. Just for fun she poured the tapioca balls into her Assam iced tea and drank it.
引用:CNN Travel Bubble tea: How did it start?
春水堂のMs. Lin Hsiu Huiが、スタッフミーティング中にアッサムティーにタピオカパール(粉圓)を入れたのがきっかけで、タピオカティーが誕生しました。それが発明のきっかけで、その後商品として、売り出していきます。
粉圓のタピオカをお茶の中に入れるという発想はここから生まれたのね
春水堂と翰林茶館のどっちが起源説は、どっちも主張を譲らずに台湾でも裁判にまで発展したらしいの
個人的にはどっちもそれぞれ同時期に発見したもんだと思うな、商品開発でいろいろ試す中で見つかるかも
その後90年代になるとタピオカミルクティーを扱うティースタンドが続々と出来て増加していき、タピオカミルクティーの人気は台湾全土へ広がっていきます。
そして台湾のティースタンドは海を越えて世界各国へ。今では世界中の人々に愛されるドリンクとなりました。
90年代以降の説明あっさりだね。。。
タピオカミルクティーの日本史

ここからはタピオカミルクティーの日本史です。日本では第三次ブームと言われてますが、第一次や第二次とは何だったのかをおさらいしてみます。
1993年 タピオカココナッツミルクが注目を浴びる【第一次タピオカブーム】
 画像引用:シェフごはん タピオカココナッツミルク
画像引用:シェフごはん タピオカココナッツミルク
第一次ブームはバブル真っ只中の1990年代前半です。この頃はエスニックブームで、ココナッツミルクが流行りました。写真のように小さなタピオカが入っていますが、どちらかというとココナッツミルクの方が主役だったようです。
今でもタイ料理屋さんとか行くとよくあるやつね。ランチタイムは食べ放題なお店もちらほら。
2001年 有限会社ネットタワーが日本初のタピオカ工場を設立
台湾出身の江野俊銘氏が、日本でタピオカ卸業の会社、有限会社ネットタワーを設立します。そして日本初のタピオカ工場(現タピオカワールド)を作りました。現在のタピオカブームにおいてもタピオカワールドからタピオカを仕入れているお店も多いと思われます。
もともとはネットビジネスを行うために設立した「ネットタワー」が、工場を借りてタピオカ生産を行うまでの流れは、タピオカマニア必見!
こういった創業の裏話は大好きなので、出版社の方々是非企画をお願いします!
2003年 有限会社ネットタワーがパールレディを出店
 そしてネットタワーが次に手を付けたのがタピオカティースタンド「パールレディ」の設立です。実業家の江野氏は、店舗運営単体ではなく、タピオカの販売と複合での飲食事業を考えていました。
そしてネットタワーが次に手を付けたのがタピオカティースタンド「パールレディ」の設立です。実業家の江野氏は、店舗運営単体ではなく、タピオカの販売と複合での飲食事業を考えていました。
ただ、当時は、販売しても売れないんです。だって、日本人は知らないんですから。それで始めたのが飲食事業です。そう、うちの飲食事業は『タピオカ』を販売するきっかけになればとスタートしたんです」。
タピオカを販売するための飲食事業(パールレディ)だと!?
当初は飲食事業のパールレディを創業してみても、まだまだタピオカの知名度は低い状況でした。そんな中、江野氏は当時人気のあったクレープ専門店に注目します。
「タピオカドリンクをメニューに加えることで、どう店全体の売れ行きがアップするか」まで考えた。それがのちのプロデュース事業にもつながっていく。
なかでも、クレープショップ専門店に仕掛けたタピオカドリンクとクレープのコラボは、圧倒的に消費者に受け入れられ、そのショップは1年で70店舗を出店するまでに成長した。
クレープ屋とのコラボに、飲食のプロデュース。なんたる商才。。。
 タピオカとクレープのセット販売の名残は今でもパールレディに残っている
タピオカとクレープのセット販売の名残は今でもパールレディに残っているパールレディは店舗運営だけでなく、タピオカの販売や飲食のプロデュースで、着々とタピオカの知名度を向上させ、タピオカ市場を拡大させていきました。
その後の第二次タピオカブームの地盤を整えたといっても差支えないでしょう。
ちなみにこの頃に学園祭で飲んだのが僕の人生初のタピオカドリンクです!
その情報必要?
2008年 台湾タピオカブランドが日本初上陸【第二次タピオカブーム】
 画像引用元:Quickly
画像引用元:Quickly
第二次ブームは、Quickly,Easywayというブランドが台湾から上陸した時期でもあります。さらにコンビニでもタピオカ系のドリンクが販売されだし、注目を集めました。
正直、この時期のタピオカブーム全然知らない。。。
第二次ブームの情報少なくない?
2013年 春水堂が日本初出店
 2013年にタピオカミルクティーの老舗、春水堂がついに代官山の地に日本初出店を果たします。そして、本格的なドリンクやフードが楽しめるということで、台湾好きの人が集まる人気店となりました。ただし今のタピオカブームと異なるのは、春水堂上陸時はタピオカのみならず台湾料理や台湾スイーツなど全体的にスポットが浴びていた感じです。客層も高めで、落ち着いた雰囲気の店内での飲食を軸に置いた店舗でした。
2013年にタピオカミルクティーの老舗、春水堂がついに代官山の地に日本初出店を果たします。そして、本格的なドリンクやフードが楽しめるということで、台湾好きの人が集まる人気店となりました。ただし今のタピオカブームと異なるのは、春水堂上陸時はタピオカのみならず台湾料理や台湾スイーツなど全体的にスポットが浴びていた感じです。客層も高めで、落ち着いた雰囲気の店内での飲食を軸に置いた店舗でした。
タピオカブームというよりは、台湾ブーム的な時期だったかも
2015年 GongChaが日本初出店
 現在のタピオカブームの代表格のゴンチャは、2015年に日本初出店を果たします。お隣の韓国では大成功を果たしたゴンチャですが、表参道のオープン当初は現在のような大行列はなく、ほんとに一部のタピオカ好きが訪れるといったお店でした。その後ゴンチャが爆発的に店舗数を伸ばし始めるのは、そこからもう2年先のお話です。
現在のタピオカブームの代表格のゴンチャは、2015年に日本初出店を果たします。お隣の韓国では大成功を果たしたゴンチャですが、表参道のオープン当初は現在のような大行列はなく、ほんとに一部のタピオカ好きが訪れるといったお店でした。その後ゴンチャが爆発的に店舗数を伸ばし始めるのは、そこからもう2年先のお話です。
2017年2月 CoCo都可が渋谷センター街に初出店【第三次タピオカブームのきっかけ】
 そして2017年に入り、いよいよ第三次タピオカブームが訪れます。そのきっかけとなったのは同年2月にできたCoCo都可渋谷センター街店といえるでしょう。
そして2017年に入り、いよいよ第三次タピオカブームが訪れます。そのきっかけとなったのは同年2月にできたCoCo都可渋谷センター街店といえるでしょう。
タピオカブームのきっかけに関してはメディアで様々な考察がされていますが、ブームを作ったのは2017年秋に渋谷や新宿に台湾のタピオカブランドの店舗数が急増したことが大きいです。
ではなぜ2017年秋から台湾のタピオカブランドの出店数が急増したのか。その答えはInstagramのストーリーズの影響だと個人的には考えています。
 2016年8月にスタートしたInstagramのストーリーズ機能は、若者のSNS投稿数を爆発的に高めました。投稿が1日で消えるという手軽さは、通常投稿に比べハードルを下げ、自分が体験したことを手軽に投稿できるという点で、ブームが作られやすい状況ともいえます。
2016年8月にスタートしたInstagramのストーリーズ機能は、若者のSNS投稿数を爆発的に高めました。投稿が1日で消えるという手軽さは、通常投稿に比べハードルを下げ、自分が体験したことを手軽に投稿できるという点で、ブームが作られやすい状況ともいえます。
ストーリーズ機能リリースから半年という最高のタイミングで、なおかつ渋谷センター街というブームの発端ともいえる最高の立地に出店したのが、CoCo都可渋谷センター街店だったのでした。
2017年9月以降 The Alley・Chatimeが日本上陸&Gongchaの出店スピードが加速【第三次タピオカブーム勃発】
 CoCo都可渋谷センター街店からの流行をきっかけに、若い世代を中心にタピオカブームが生まれ始めます。タピオカの味や食感にハマりだす人が続出し、飲んだり、投稿したり、調べたりと、若い世代に「タピる」人が続出します。
CoCo都可渋谷センター街店からの流行をきっかけに、若い世代を中心にタピオカブームが生まれ始めます。タピオカの味や食感にハマりだす人が続出し、飲んだり、投稿したり、調べたりと、若い世代に「タピる」人が続出します。
 そして2017年秋、台湾のタピオカブランドが続々と日本出店を果たします。ChatimeやTheAlleyといったブランドが出店を果たし、Gongchaは出店数を加速させていきます。
そして2017年秋、台湾のタピオカブランドが続々と日本出店を果たします。ChatimeやTheAlleyといったブランドが出店を果たし、Gongchaは出店数を加速させていきます。
 そもそも世界的には欧米やアジア圏でも、既にタピオカドリンク市場は加熱している状況でした。そんな中、輸入障壁や日本語の言語障壁で遅れていた日本で、2017年にようやく起きたタピオカブーム。そんな小さなきっかけを、世界展開する台湾ティースタンドは見逃すことがありませんでした。
そもそも世界的には欧米やアジア圏でも、既にタピオカドリンク市場は加熱している状況でした。そんな中、輸入障壁や日本語の言語障壁で遅れていた日本で、2017年にようやく起きたタピオカブーム。そんな小さなきっかけを、世界展開する台湾ティースタンドは見逃すことがありませんでした。
2018年 台湾ブランドが続々上陸&国内新規ブランドも続々誕生
 2018年にはさらに、台湾のティースタンドが日本に続々出店。新たに店を開けば行列ができるという状況のなかで、各店こぞって出店をしていきます。
2018年にはさらに、台湾のティースタンドが日本に続々出店。新たに店を開けば行列ができるという状況のなかで、各店こぞって出店をしていきます。


そして、国内発のブランドが続々と誕生していったのもこの時期です。日本のタピオカ市場はかつてのブームとは比較にならない規模で大きくなり、話題にも取り上げられています。
いずれはこのブームは収束するでしょう。ただ、台湾のみならず中国や韓国、さらには欧米の状況と比べてみても、ブームだけで終わることなくピークを過ぎてもティースタンド自体は定着すると思います。
20年前にアメリカシアトル発のコーヒーチェーンが日本に上陸し、その後拡大していったように、台湾発のティースタンドも、ブームの先の競争に勝ち残ったブランドが、定着するのではないでしょうか。

【主要タピオカ店おすすめメニューランキング】
【タピオカ激戦区全店紹介&ドリンクBEST5】
渋谷のタピオカミルクティー専門店全20店紹介&ドリンクBEST5をタピ愛好家が真剣に決めてみた
原宿・表参道のタピオカミルクティー専門店全20店紹介&ドリンクBEST5をタピ愛好家が真剣に決めてみた
新宿のタピオカミルクティー専門店全20店紹介&ドリンクBEST5をタピ愛好家が真剣に決めてみた
【山手線エリアのタピオカ店】
恵比寿のタピオカミルクティー専門店4選!全部回ったのでまとめました
新大久保のタピオカミルクティー専門店10選!全部回ったのでまとめました
高田馬場のタピオカミルクティー専門店10選!全部回ったのでまとめました
池袋のタピオカミルクティー専門店16選!全部回ったのでまとめました
秋葉原のタピオカミルクティー専門店2選!全部回ってみたのでまとめました
有楽町・銀座のタピオカミルクティー専門店6選!全部回ってみたのでまとめました
【その他エリアのタピオカ店まとめ】
浅草のタピオカミルクティー店5選!全部回ってみたのでまとめました
お台場のタピオカミルクティー店3選!全部回ってみたのでまとめました
下北沢のタピオカミルクティー店5選!全部回ってみたのでまとめました
代官山・中目黒のタピオカミルクティー店6選!全部回ってみたのでまとめました
自由が丘のタピオカミルクティー店10選!全部回ってみたのでまとめました
吉祥寺のタピオカミルクティー店10選!全部回ってみたのでまとめました
飯田橋・水道橋のタピオカミルクティー店8選!全部回ってみたのでまとめました
赤羽のタピオカミルクティー店3選!全部回ってみたのでまとめました
大宮のタピオカミルクティー店4選!全部回ってみたのでまとめました
 「毎日の生活を少し豊かにする」台湾茶のティーバッグを販売してます。
「毎日の生活を少し豊かにする」台湾茶のティーバッグを販売してます。
自宅で簡単に淹れられる四季春茶・焙煎凍頂烏龍茶・木柵鉄観音茶・東方美人茶・台湾蜜香紅茶・台湾ジャスミン茶を取扱中です。